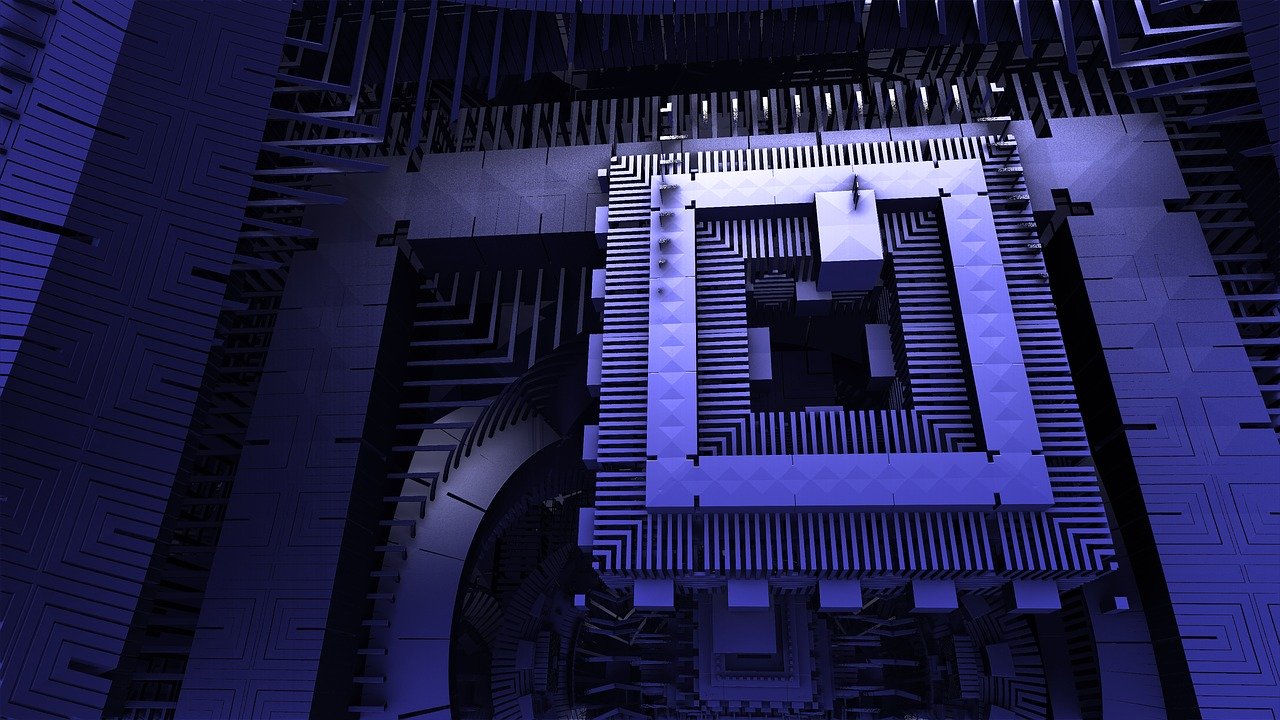
量子コンピュータの開発による仮想通貨への影響
量子コンピュータは、1982年に量子力学的に並列処理を実現することのできるコンピューターであると提唱され開発に取り掛かったことが始まりです。
さて、量子力学的並列処理の実現の説明の前に、比較の為に、現在、私達が使っているコンピューターについて説明をします。
現在使われているコンピュータは、量子コンピュータと比べるために、古典コンピュータと呼ばれています。
私達が使っているコンピュータは量子コンピュータの前では古いものという扱いなんですね。
古典コンピューターの情報の基本単位をビットと呼び、おのおの0か1のどちらかの状態で、2進数での演算を行っています。
データは「0」と「1」の組み合わせで表現されます。
具体的には、0か1の切り替えは電流を入れたり、切ったりと切り替えて(ON/OFF)表現しています。
古典コンピュータは0か1の状態で演算をおこないますが、量子コンピュータは古典コンピュータと何が違うのでしょうか。
量子コンピュータは、基本単位の情報を複数、同時に保持(重ね合わせ)することができます。
複数なので2つ以上の状態を同時に表すことが可能なんです。
人間で言えばテレビを見ながら本を読み更には絵を書く行為を全て同時に行える
ようなものです。(実際には無理ですが)
量子コンピュータの重ね合わせの情報単位のことを「量子ビット」と呼びます。
量子コンピュータの計算能力は従来のコンピューターのトップであるスーパーコンピューターよりも1億倍の演算能力があるとも言われています。
そんな量子コンピュータの実用化に向けてNASAやGoogleが心血を注いで開発中です。
2018年12月にIBMは、IBMQというプロジェクトで開発した量子コンピュータがスーパーコンピュータの演算処理能力を上回ったと発表しました。
さらにGoogleは、現在の最高性能のスーパーコンピュータである“サミット”をもってしても、1万年はかかるだろうと言われた計算を量子コンピュータで僅か3分20秒で解いてしまったのです。
スーパーコンピュータで膨大な時間がかかる計算を量子コンピュータが短時間で解いてしまうという量子超越性を示す一例になります。
量子コンピュータが実用化されれば、私達の生活がより便利で快適になることでしょう。
しかし、量子コンピュータが実用化されるとよいことばかりではありません。
量子コンピュータの処理能力を悪用されるとインターネット上で使用される暗号が解読されてしまう恐れがあります。
今までは無理だろうと言われていた仮想通貨の「秘密鍵」(暗号)も解読される恐れがあると危ぶむ意見も出ています。
量子耐性とは?
量子耐性とは量子コンピュータにも暗号を解読されない、若しくは解読に時間がかかるように量子コンピュータの暗号解読の対策ができていることを示しています。
量子耐性を持たせるための対策として以下のようなものがあります。
・秘密鍵の暗号を強化する
秘密鍵の長さを従来よりも長くしたり、より解読されにくい複雑なタイプにし量子耐性を得ようとする方法です。
・3進数を使用する
現在コンピュータで使われているのは、2進数がメインで使われています。
当然量子コンピュータも2進数に対応してくるので、あえて3進数を使用するという方法です。
量子コンピュータも計算が難しくなります。
・ハッシュ関数を難しくする
ハッシュ関数とは、与えられたデータを導き出すのに必要な数字を手に入れるための関数です。
ハッシュ関数は例えば1という数字を入れると、全く違った記号に置き換えられます。
この関数の法則をより難しくして解読されにくくしようという方法です。
・ワンタイムパスワード
1度限りの使い捨てのパスワードです。
ネットバンクや仮想通貨の取引所でよく使われています。
1度きりのパスワードなので、もし解読をされてしまっても、すぐに使用出来なくなるのでセキュリティ効果は高いです。
・ランポート署名
量子コンピュータの暗号解読に耐性があるとされているのがランポート署名です。
1979年にレスリー、ランポートにより考案されたのでランポート署名とよばれています。
ランポート署名は署名者が256対つまり512個の秘密鍵と秘密鍵をハッシュ化した公開鍵を生成します。
このハッシュはだれでもみることはできますが、初めの乱数を求めるのは量子コンピュータでも解読に手こずるはずです。
次に署名者の署名を行います。
メッセージを256ビットの2進数に変換し、メッセージごとに決められたハッシュを計算し、256個の乱数を手に入れたら、署名を受け取った人が署名のメッセージのハッシュをつくり、署名者の公開鍵と一致すれば改ざんはされていないということが分かるわけです。
今までの署名よりも安全で、量子コンピュータにも耐えられるとされているのがランポート署名です。
量子コンピュータの暗号解読の最悪の事態を回避するために様々な対策が練られていることが分かるかと思います。
量子耐性型と言われる仮想通貨の例
・Cardano(カルダノ)
イーサリアムの操業やイーサリアムクラッシックの開発に携わっているチャールズホスキンソン氏が開発した仮想通貨です。
イーサリアムよりも優秀なスマートコントラクトPlutusを実装していたり、独自のマイニングウロボロスを実装した仮想通貨です。
量子コンピュータ対策にBLlISS署名という署名アルゴリズムでブロックチェンに書き込み量子耐性としています。
・IOTA(アイオータ)
物と物との繋がりを便利にし決済が早くでき手数料が無料にできるととにかく便利な仮想通貨です。
アイオータは、そもそも暗号を解読するための項目が独自のものであり、解読する時間も今までと変化がないため安全性が高い通貨と言えるでしょう。
・Quantum Resistant Ledge(クオンタム レジスタントレジャー)
量子コンピュータの脅威から守る量子耐性に重きを置いた仮想通貨です。
XMSSと言う署名で量子コンピュータの攻撃から守ってくれます。
仮想通貨の取引や送金などの個人情報をXMSSで処理し、データの改ざんを防いでくれます。
・Shield(シールド)
Verge(XVG)を母体として作られた通貨です。
FacebookやTwitterなどのSNSで使われることを目指している仮想通貨です。
匿名性に優れており、早くから量子耐性を意識していた通貨であります。
様々な機能を実装していこうという姿勢が強く見られる通貨です。
・Nexus(ネクサス)
ネクサスアースと呼ばれるネットワークを使いみんなが平等に使用できるネットワークをつくりあげようとしています。
1024ビットでハッシュ化していることや1度きりしか使えない秘密鍵と量子耐性がされている通貨です。
しかし、こうした量子耐性の対策をしていると公式に発表しておらず、結果的にそうなったという話かもしれません。
量子耐性を持っている通貨は匿名通貨が多く持っている傾向があるようです。
プライバシーを守るということに重きをおいている通貨の性格上セキュリティに対して敏感ということなのかもしれません。
以上、量子耐性をもつ仮想通貨を見てきましたが、まだまだその普及割合は低い状況です。
今後、量子コンピュータの開発が進む中で安心して仮想通貨の取引、保管ができる環境が整えられることを期待したいですね。

